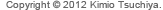REVIEWレビュー
「記憶」呼び起こすもの求めて

記憶の風景JR川崎駅西口に完成して間もない再開発ビルの入り口。傾いた赤レンガ倉庫の前を、人影が流れていく。ガラス張りの高層建築と不思議な対照を見せるそれが、「記憶の風景」と題する近作だ。
「日本の都市は新しくつくるために古いものを壊していく。歴史や時間や記憶、自分とは何かと問いかける手がかりも一緒に失ってしまう。それが加速化しているという思いが、すごくあるんですよ」
かつてこの辺りには、90年前に建てられた旧国鉄の変電所があった。
その正面部分を再現し、関東大震災や空襲に耐えた来歴を文字に刻んでいる。大きく左にかしいだ姿は、失われた光景が地下からせり上がってくるかのようだ。

虚構
記憶の部屋「記憶」「所在」といったテーマをめぐる作品を発表してきた。
さかのぼれば大学時代、夏目漱石を読み返して出合った、「所在のないほど悲しい人間はいない」という言葉に行き着く。消費社会に育ち、情報過多の中で何をしたいのか見えない自分もまた、所在ない人間と感じた。卒業後はヨーロッパを旅行し、そこでイギリスのリチャード・ロングをはじめ、現代美術の作品に出合う。30歳を過ぎてロンドンの美術大学の大学院に入り直した。
「アートは時代とかかわりながら表現が成立している。石をサークル状に並べただけのロングの作品なども、初めは難解で分からなかったが、生きているあかしを残すことなんだと思うと、すっと自分の中に入ってきた」と話す。
初めは、宅地開発で伐採され、ブルドーザーに踏みつけられた自然木や、東京・夢の島に漂着する流木を集めて作品にした。
「僕が使う素材は、すべて人間がかかわっている」と語る通り、現代社会が排除し、打ち捨てたもの。
90年代には解体された家屋の建材、家具、電化製品、本などを組み合わせた「虚構」「記憶の部屋」などの立体作品で注目された。そこに住んでいた家族の記憶を封じ込めた作品、と受け取られがちだが、実は自分の記憶を呼び起こすものを求めていた。たとえばタンスに残る樟脳の香りに、ふと入学式で母親が着ていた着物の色を思い出す。
「人間の記憶はコンピューターのメモリーにしまい込まれた記憶と違い、感覚や感情など身体性と深くかかわっている。記憶がよみがえるのは、今の自分が反応するから。常に『現在』と連続していると思うんです」

大洪水の後で鉄の小部屋の内壁に、びっしりと時計を並べた「大洪水の後で」(2002年、サンパウロ・ビエンナーレ出品)も、時計修理を営んでいた父親にまつわる作品だ。
「家の中は時計だらけ。熱で寝ている時など、一斉にボンボンと鳴ってたまらなかった」と笑う。
その父親を亡くしたのは、廃材を燃やした灰による作品を作り始めた時期。物質的な存在を消すと何が残るか、と試みていたが、生命の行き着く先は同じ灰なのだ、という思いを強くした。しかし、死や終末のイメージはない。
「まるっきり逆で、再生の象徴なんです。父親も、今では生きている時よりリアルさをもって僕の中に存在している」という。最近の変化は、その延長から生の象徴として花を使うようになったことだ。

記憶の場所
3年前、東京・墨田区の横網町公園に造った東京空襲の追悼モニュメントは、扇形の花壇を持つ。花は一人一人の生を示し、年4回の植え替えなど、手間をかけることで犠牲者たちを忘れさせまいとした。
「僕はアートの力を信じている」とてらいなく語る。
今どき安く見られかねない言葉を口に出来るのは、私的な記憶に端を発した作品が、いつか普遍性へと通じる手応えを信じるからに違いない。
讀賣新聞 掲載記事
文:高野清見